古代ローマの朝は早く、夜明けと同時に人々が動き出します。
というのも電気のない時代、照明の為の油も安くはないため人々は夜は早めに眠りにつきました。
奴隷達は夜明け前から起きて仕事を始めるのでした。
そんな古代ローマの庶民の朝ごはんはどんなものかというと…
朝ごはんは食べない、もしくは昨日の残り物やパンで軽く済ませるのが普通でした。
古代ローマの朝の習慣を研究する際に、よく用いられる資料に「学童の一日」について記した教科書のよう文章があります。
よい子の模範的な生活が綴られたものです。ちょっと引用してみましょう。
“ぼくは夜明け前に目を覚まします。ぼくはベッドから起きます。
ベッドに腰掛けて、靴下と靴をはきます。
ぼくは顔を洗うために水を持って来させます。ぼくはまず両手を洗い、それから顔を洗いました。手ぬぐいでふいて乾かしました。
ねまきを脱ぎました。それからトゥニカ(下着)をつけました。ベルトをしめました。髪に油をつけて、櫛をいれました。
両肩にスカーフを巻きつけました。その上から白い外套を着、さらにその上に雨降り用のマントを羽織りました。
教育係の奴隷と乳母を従えて寝室を出、父と母に挨拶に行きました。ぼくは二人に挨拶し、口づけをしました。それから家を出ました。
ぼくは学校に行きました。ぼくは学校に着くと、「先生、こんにちは」と言いました。(以下略)”
朝ごはんを食べずに学校へいく様子がわかります。
しかし、それではお腹が空きそうですね。
実は、朝ごはんに食べる蜂蜜入りの菓子パンや揚げパンのようなものを売る屋台が街中のあちこちにありました。子どもたちや肉体労働をする人々など、朝ごはんを食べないとお昼までもたない人は、屋台で軽食を買い食いする事も多かったようです。

ポンペイの通りと蜂蜜菓子を売る屋台の想像図
庶民に比べて貴族たちは朝に何を食べるか、たくさん食べるのか、などの選択肢がありました。人によっては朝から豪華な食事をとることもありました。
しかし、朝ごはんをたくさん食べる事はあまりお上品な事とはされなかったようです。ローマ帝国の6代目の皇帝となったガルバという人物は、贅沢な食事をするタイプではなかったものの、朝ごはんはしっかり食べる派だったらしく、
“彼は大食漢であったと伝えられている。冬の季節には夜明け前にも食事をとる慣わしであった”
とわざわざ書かれています。
ローマ帝国8代目の皇帝ウィテリウスは朝から饗宴でご馳走ざんまいでした。
現在の感覚でもちょっと食べすぎな感じがしますが、古代ローマの庶民の感覚からすれば、批判を集めて当然だったのかもしれません。
その後ウィテリウスは悲惨な最期を迎えたのですが、それに関しては過去の記事に書きましたので、こちらも読んでもらえると嬉しいです。


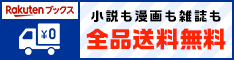











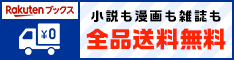



 少し品位は下がるとされたものの、たっぷり食べる事ができるレストランのような店はグルグスティウムと呼ばれました。
少し品位は下がるとされたものの、たっぷり食べる事ができるレストランのような店はグルグスティウムと呼ばれました。



